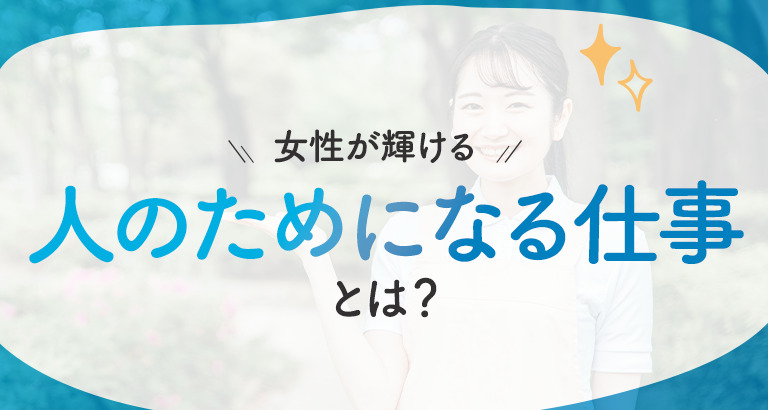
女性が輝ける“人のためになる仕事”とは?
「人の役に立てる仕事がしたい」
そんな思いを抱く女性は、今増え続けています。
働く理由は人それぞれでも、「誰かの役に立ちたい」「やりがいのある仕事をしたい」という想いは、年代にかかわらず多くの女性に共通するものです。
家庭や子育てがひと段落した40代・50代の方はもちろん、20〜30代の若い世代にも、「自分の力を誰かのために使いたい」という気持ちが芽生える瞬間があります。
この記事では、「人のためになる仕事」の具体例とその魅力をわかりやすく解説。
さらに、きずなの会での支援スタイルを通して、「人のそばで役に立つ」という新しい働き方もご紹介します。
人のためになる仕事とは?人気の仕事も徹底解説

「人のためになる仕事」とひとことで言っても、そのかたちはさまざまです。
たとえば、目の前の相手を直接支える“対人支援”もあれば、地域や社会を広く支える“社会貢献型”の仕事、誰かが安心して暮らすための“生活支援”など、貢献のスタイルには違いがあります。
自分に合った「人のためになる」の形を見つけるためには、その多様性を知ることが大切です。
「人のためになる仕事」とは、誰かの生活、心、健康、成長、安心などにポジティブな影響を与える仕事のことを指します。
直接的に支援を行う福祉・医療・教育職から、間接的に社会を支えるNPOや行政サービス、地域活動などもその範囲に含まれます。
近年では、働きながら社会貢献ができる「ソーシャルグッド」な仕事に注目が集まっています。
■ 人のためになる“役立ち方”の種類
人のためになる仕事には、次のような「役立ち方」の違いがあります。
心に寄り添うことで役に立つ
悩みや不安を抱えた人の話を聴き、精神的な支えになる仕事です。カウンセラーや相談員、福祉関係者などがこれに該当します。
肉体的なケアを通じて役に立つ
身体的な援助や介助を通じて、生活を支える職種です。看護師や介護職員などが代表例で、直接的なサポートを通じて「安心」を届けます。
知識や教育で支援する
学びや成長をサポートする教育職も、“人のため”になる仕事です。保育士や教師、支援員などは、子どもや若者の将来を育む重要な役割を担います。
暮らしを支える間接支援
役所の手続きや買い物の同行、生活面の支援など、目立たないけれど欠かせない“縁の下の力持ち”的な役割です。きずなの会の生活支援員はこの領域に該当します。
■ 女性に人気の“人のためになる仕事”
看護師・保健師
医療の最前線で人の命や生活を支える職種。専門性とやりがいを両立でき、復職支援も充実しているため、ブランクのある女性にも人気です。
保育士・幼稚園教諭
子どもの成長を見守る仕事は、育児経験のある女性にも人気。子どもたちの「できた」を支える喜びや、日々の成長を感じられる点が魅力です。
介護職(訪問介護・施設介護)
高齢者の生活を支える職種。人と深く関わる分、やりがいも大きいですが、資格支援制度や研修制度が整った施設も多く、未経験から挑戦しやすい分野でもあります。
カウンセラー・相談員
心理的な不安や生活上の悩みを抱える人に寄り添う仕事。自治体、NPO、教育機関など幅広い場で活躍の場があり、共感力や傾聴力を活かせる職種です。
NPOスタッフ・地域支援職
子育て支援、障がい者支援、災害対応など多岐にわたる社会課題の現場で活動。給与面では民間企業に劣ることもありますが、「想い」を軸に働けるという点で高い満足度を得られるケースも多いです。
■ こうした仕事に共通する“やりがい”とは?
“人のためになる仕事”には、共通して次のようなやりがいがあります。
- 誰かの笑顔や「ありがとう」に直接触れられる
- 支援を通じて相手の変化や成長を感じられる
- 自分の仕事が社会に役立っていると実感できる
年齢にかかわらず、多くの女性が日々の生活や人間関係を通じて、人の話を聴く力や気配り、柔軟な対応力といった“人間力”を自然と身につけています。
こうした力が活かせる職種だからこそ、誰でも挑戦しやすく、活躍の場が広がっているのです。
「誰かのために役立っている」と実感できることが、働く意欲にもつながる
それが「人のためになる仕事」の魅力です。
きずなの会で「人の役に立つ」

“人のためになる仕事”にはさまざまな形がありますが、実際にどんな現場で、どのような支援が行われているのかを知ることで、より具体的なイメージが持てるようになります。
ここからは、身体介助を伴わない新しい福祉の形として注目されている、きずなの会の「生活支援員」の取り組みをご紹介します。
■ 生活支援員という“第三の仕事”
きずなの会では、一般的な介護とは異なる“生活支援員”という職種を展開しています。
身体介助や医療行為は行わず、高齢者や身寄りのない方の生活に寄り添うサポート役として、独自の支援スタイルを確立しています。
主な業務内容は、
- 病院や施設の入退院時の付き添い
- お買い物や日用品の代行
- 役所や金融機関などの手続きサポート
- 身元保証や死後事務といった人生後半の“安心”の支援
まさに、現代社会における“縁の下の力持ち”として求められる存在です。
■ 未経験・40代からでも活躍できる理由
きずなの会では、介護資格や実務経験がなくても、「人の話を聴くのが好き」「人に寄り添いたい」という思いがあれば活躍できます。
現在活躍中のスタッフの多くも、40代・50代で未経験からスタートしています。
- マニュアルに沿った丁寧な研修制度
- チームで支え合う風土
- 無理のない勤務体制やシフト相談のしやすさ
といった職場環境が、安心して働き続けられる理由です。
■ 「ありがとう」が直接届く仕事
日常のちょっとした「困った」を一緒に解決する中で、「ありがとう」「助かりました」という言葉を直接受け取れる機会が多いのも、生活支援員の特長。
「人の役に立っている」と実感できる、やりがいある仕事を探している方にとって、きずなの会の生活支援員は非常に相性の良い職種といえるでしょう。
まとめ

「人のためになる仕事」は、誰にとっても挑戦しがいのある分野です。
人生経験を積んだミドル世代の女性はもちろん、20代・30代の若い方にとっても、人に寄り添う姿勢や共感力が大きな武器になります。
きずなの会の生活支援員は、介護のように体力を要する仕事ではなく、「誰かのそばにいること」そのものが支援になる新しいスタイルの仕事です。
これまでの人生で培ってきた思いやりや気配りが、今、誰かの“安心”につながる。
そんな仕事に、一歩踏み出してみませんか?
他の採用ブログ OTHER TOPICS
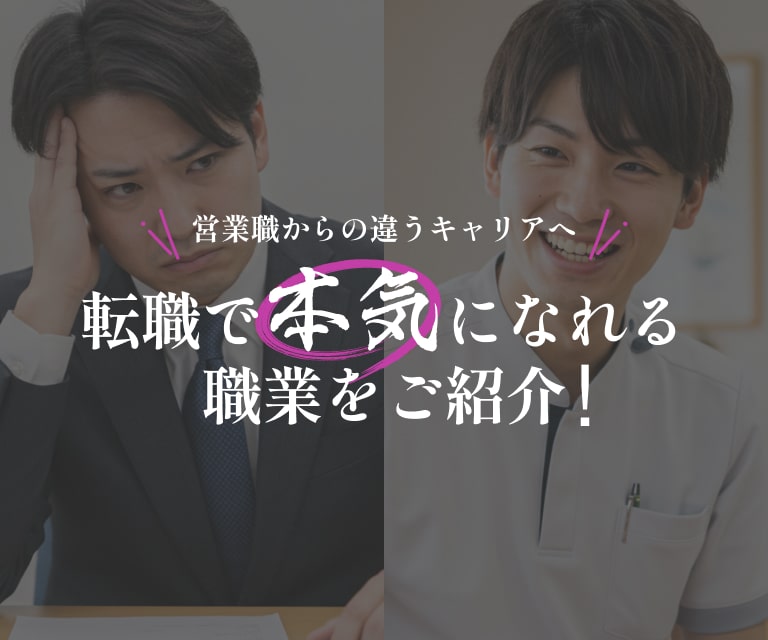 お知らせ
お知らせ
営業職からの違うキャリアへ!転職で本気になれる職業をご紹介
 お知らせ
お知らせ
50代⼥性必⾒!必要とされる!⼥性が活躍できる仕事とは?
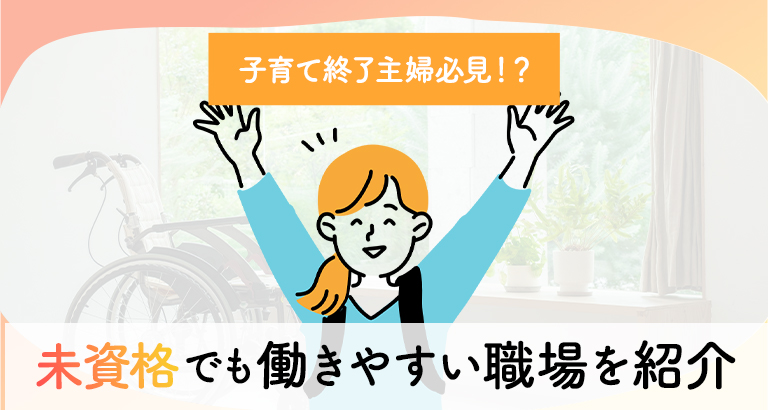 お知らせ
お知らせ
子育て終了主婦必見!?未資格でも働ける働きやすい職場を紹介
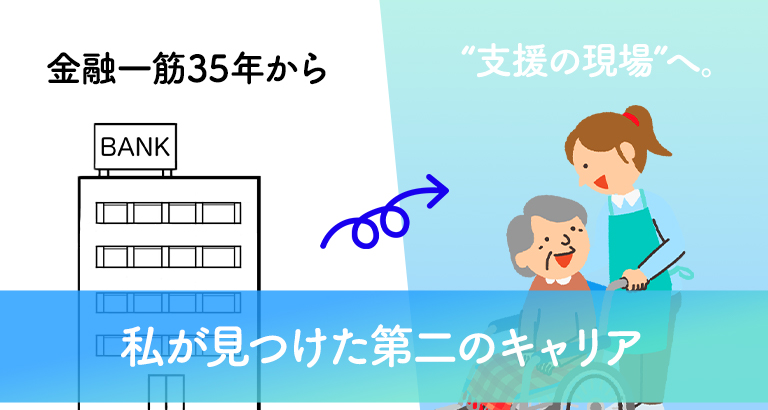 お知らせ
お知らせ
金融一筋35年から“支援の現場”へ。私が見つけた第二のキャリア
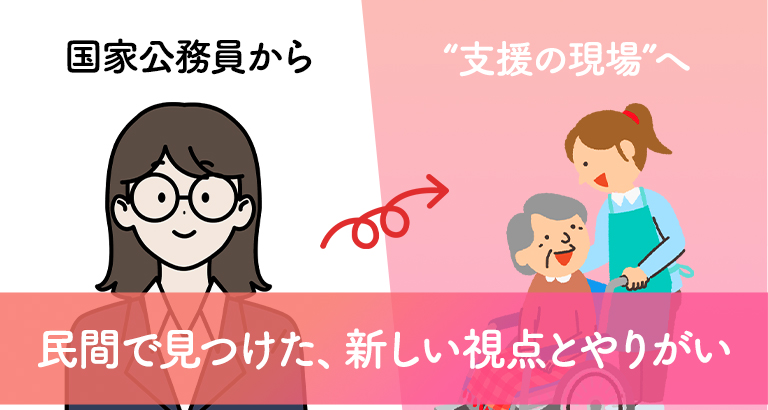 お知らせ
お知らせ
国家公務員から“支援の現場”へ。民間で見つけた、新しい視点とやりがい
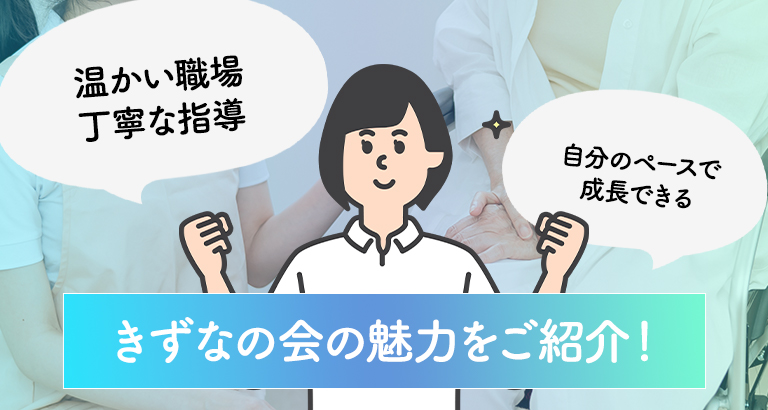 お知らせ
お知らせ
温かい職場、丁寧な指導。自分のペースで成長できる。そんな魅力を皆さんに伝えたい。

